
冷蔵庫の中で使われる脱臭剤や靴底に敷くデオドラントシートなど, 我々の身の回りには吸着材と呼ばれる物質を多く用いていることは, 一般市民でも少しは知っていることであろうか。吸着材は生活と密接に関係する物質であり, 現象である。このように吸着という現象は, ありふれているけれども, 一般市民にとってはあまりなじみのない言葉かもしれない。「くっつく」「吸いつく」といった方がわかりやすいように思える。ただ, 「くっつく」というと接着が思い浮かんだり,「吸いつく」というと吸引というイメージにつながる。一般の方々に吸着とは何かを, わかりやすく簡潔に説明するのは結構難しいのである。やはり, 「活性炭で臭いをとったり, 浄水したりするのが吸着である」と説明する方がよほどわかりやすいであろう。しかしながら, では吸着とはどんな物理化学現象なのだろうかとなると, 結局わかってもらっていない。これは一般市民のみならず, 工業に携わる技術者の方々でも, 例外ではない。
前述のように, 吸着現象を利用した製品や施設, システム, プロセスなど様々なものが我々の生活においてなくてはならないものとなっている。このことを, よく理解してもらっていないのであれば, 知ってもらおうというのが, この本の趣旨である。特に工業に携わる研究者や技術者の方に, 吸着分野が応用されている産業やその具体例, また, 産業分野において吸着現象と関わる要素技術について, できる限り広い範囲で紹介しようというねらいから, このハンドブックを作成することとなった。当然, 企業の研究者や技術者の方々からの意見を反映させて, 内容をまとめてある。
小難しい理論などは後の方に回してあるので, 早い段階で応用事例に出くわすことになる。また, 以前からハンドブックなどで紹介された物質や材料についても, それほど詳細には掲載してないので, これまでの吸着現象に関連するハンドブックとも, 少し変わった内容になっている。
目次を見ていただくと, 環境技術に関わる分野からエネルギー分野,バイオテクノロジーといった比較的大きな産業分野から, ドライクリーニングや浄水器といった生活関連の分野まで, 広く応用事例や要素技術を紹介することにした。また, 吸着に関わる技術で, 新たな分野もまとめてある。すべての産業分野における吸着技術の応用例を網羅できれば万全であるが, 当然吸着と関わる産業分野であっても, そのような観点からの研究や技術的な考察がなされていない分野もある。特にエレクトロニクスなどの先端産業において, 吸着現象が関わる応用分野は大きいと思われるが, その観点から考察されていない。このハンドブックの応用事例を参考にしていただければ, 必ず, その他の産業分野でも吸着と密接に関わっていることが実感できると確信する。
このように, 特に吸着を専門とする方以外の研究者や技術者の多くの方々に本書を見ていただき, 現在携わっている現象の解明や改良, 今後の新規分野への展開において, 有益な知見を与えられればと期待している。
(千葉大学 加納博文)
編集委員長 金子 克美 千葉大学理学部化学科 教授
編集委員 廣津 孝弘 産業技術総合研究所
進戸 規文 元大阪ガス
安武 重雄 荏原エンジニアリング
伊藤 睦弘 富士シリシア化学
加納 博文 千葉大学
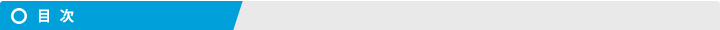
序章 吸着技術とは
1 吸着とは
2 吸着のメカニズム
2.1 気相吸着
2.2 液相吸着
3 吸着材の分類
第1章 吸着現象の応用事例
1 吸着材
a) 炭素系
1 概論
b) シリカ系
1 シリカ系吸着剤
2 シリカゲルの製造法
2.1 珪酸ソーダ
2.2 酸による分解
2.3 ゲル化
2.4 水熱処理と乾燥
2.5 細孔径制御
3 シリカゲルの物性と吸着特性
3.1 シリカゲルの物性
3.2 吸着特性から見た用途
4 シリカゲルの選択吸着性能
4.1 シリカゲルの表面
4.2 シリカゲルの表面シラノール基と液体クロマトグラフィー
5 吸着剤の劣化
6 まとめ
c) ゼオライト 系
1 ゼオライトについて
2 ゼオライトを用いた分離技術
3 ゼオライトによる調湿効果
4 おわりに
d) 金属錯体を用いた新規ガス吸着材
1 はじめに
2 金属錯体
2.1 {CuSiF6(4,4-bipyridine)2}n1
2.2 {Zn2(p-(OOC-Ph-COO))2}n
2.3 {Zn4(O)(p-(OOC-Ph-COO))3}n
2.4 {Cu2(pzdc)2(L)}n (pzdc = pyrazine-2,3-dicarboxylate: L = a pilar
ligand)
2.5 {Cu3(1,3,5-C6H3(COOH)3)2}n
3 天然ガス吸着貯蔵
4 金属錯体の合成法、構造および物性評価
4.1 二次元ジカルボン酸銅錯体(Square Plane Structure)
4.2 三次元ジカルボン酸銅錯体(Octahedral Structure)
4.3 外場応答型金属錯体
5 最後に
e) イオンふるい材料
1 はじめに
2 イオン鋳型反応によるイオンふるい吸着剤の合成
3 イオンふるい作用
4 細孔径の評価と応用
2 産業における応用事例
a) 水処理
1 はじめに
2 活性炭の種類
3 上水・用水処理
3.1 異臭味除去
3.2 消毒副生成物の低減
3.3 残留塩素の除去
4 水・廃水処理
4.1 工場排水処理
4.2 し尿処理、ゴミ埋立地浸出水処理
4.3 下水高度処理
b) 液体の回収・除去
1 下水処理水の高度処理事例
1.1 修景用水としての高度処理事例
1.2 工業用水等としての高度処理検討事例
2 ボイラブロー水からの水回収システムの開発事例
2.1 ヒドラジンの分解機構
2.2 水回収システムのフローと回収水の目標値
2.3 活性炭によるヒドラジン処理結果
2.4 UF(Ultrafiltration)膜処理結果
3 醸造工場排水の再利用事例
4 研究所排水の再利用事例
c) 天然ゼオライトを用いた海水からの農業用栽培用水の製造
1 はじめに
2 天然ゼオライトによる海水の改質
3 二段階による農業用水製造プロセス
4 おわりに
d)火力発電所の海水温排水からのリチウム採取技術
1 はじめに
2 リチウム吸着システムの流動状態とリチウム吸着量
2.1 リチウム吸着システムの概念図
2.2 模型実験によるリチウム吸着の確認
3 リチウム採取の実用化を目指したパイロットプラント
3.1 火力発電所内リチウム採取システムの基本構想
3.2 パイロットプラントの運転によるリチウム採取システムの検証
e) 貴金属回収
1 活性炭による金回収事例
1.1 従来の金採取法(水銀アマルガム法)
1.2 近年の金採取法(青化法)
1.3 吸着剤(活性炭)使用する金採取法(カーボン・イン・パルプ法)
2 その他の貴金属回収事例
f) ガスの除外
1 緒言
2 大容量排ガス処理用活性炭
3 プロセスと主要機器
3.1 概要
3.2 吸着反応塔
3.3 再生塔
3.4 活性炭移送システム
3.5 副生品回収システム
4 脱硫・脱硝反応
4.1 吸着反応塔での反応
4.2 再生塔内での反応
4.3 脱硝反応の応用例
5 その他の有害物質の除去
6 おわりに
g) 脱臭技術
1 脱臭技術の概観
2 臭気の評価方法および規制値
3 臭気の評価方法および規制値の問題点
4 悪臭物質の特性と吸着
5 まとめ
h) 悪臭防止
1 はじめに
1.1 においとは
1.2 悪臭とは
2 臭気対策の(最近の)動向
2.1 悪臭防止法とその排出基準
2.2 VOC(Volatile Organic Compounds)規制
3 脱臭方法の概要
4 吸着法による脱臭
4.1 吸着剤
4.2 活性炭による吸着・脱臭
4.3 添着活性炭による脱臭
4.4 悪臭物質の吸着性(平衡吸着量)
4.5 脱臭における設計手法
5 おわりに
i) 吸着剤による脱臭事例
1 はじめに
2 脱臭に用いられる吸着剤の概要
2.1 活性炭(一般炭・無添着炭)
2.2 酸性ガス用添着活性炭
2.3 塩基性ガス用添着活性炭
2.4 中性ガス用添着活性炭
2.5 成分同時除去用特殊添着活性炭
2.6 その他
3 吸着法による脱臭技術(脱臭設備)の概要
4 事例紹介
4.1 脱臭用活性炭
4.2 固定床交換式簡易型脱臭装置
4.3 その他の簡易型脱臭装置
5 脱臭設備の設計例
6 おわりに
j) 活性炭による溶剤回収
1 はじめに
2 溶剤回収用活性炭に求められる吸着特性
2.1 溶剤回収用活性炭に求められる特性
2.2 耐摩耗性(硬さ)と耐薬品性
2.3 有効吸着量
2.4 触媒性
2.5 発火点
3 実際の溶剤回収装置例
3.1 溶剤回収装置の概略
3.2 操作上の注意点
3.3 活性炭の劣化と再生
4 さいごに
k) 炭素材によるPSA技術
1 はじめに
2 活性炭のナノ構造
3 分子篩活性炭
3.1 はじめに
3.2 活性炭と分子篩炭
3.3 分子篩炭の製造方法
3.4 分子篩炭の応用
l) 吸着ヒートポンプ
1 はじめに
2 密閉式吸着ヒートポンプ
3 開放系吸着ヒートポンプ
3.1 HSA構成
3.2 冷却特性評価に用いたシリカゲルの物性および充填層による冷熱生成確認操
作
3.3 各種シリカゲルの脱着冷却特性
3.4 ハニカムローター型吸着機によるHSAシステムの稼働特性
4.おわりに
m) ハニカムロータの応用(熱交換器とその他)
1 全熱交換器
1.1 全熱交換器の原理と構造
1.2 全熱交換器ロータ
1.3 用途及び導入事例
2 ハニカムロータ除湿機(デシカント除湿機)
2.1 吸着式ハニカム除湿ロータの種類
2.2 原理と構造
2.3 用途に応じた各種フローの例
2.4 用途及び導入事例
3 デシカント空調機
3.1 デシカント空調機の装置概要と原理
3.2 用途及び導入事例
4 ハニカムロータ型溶剤(VOC)濃縮装置
4.1 VOC濃縮装置とシステム構成
4.2 VOC濃縮ロータハニカム
4.3 用途及び導入事例
n) 吸着剤を用いたガス貯蔵システム
1 はじめに
2 メタン吸着材および吸着貯蔵システムの開発
2.1 吸着式貯蔵とは
2.2 メタン吸着材
2.3 吸着式ガス貯蔵方式
2.4 従来貯蔵法(低圧式貯蔵方式)との比較検討によるフィジビリティースタ
ディー
3 吸着式ガス貯蔵の導入事例
3.1 天然ガスへの適用事例
3.2 吸着式ガスホルダーのFeasibility Study
3.3 分離型二塔式貯蔵装置を用いた新しい天然ガスの吸着貯蔵方法
3.4 天然ガスの繰り返し吸着特性
3.5 結果および考察
4 下水処理場からバイオガスへの適用
4.1 家畜糞尿から発生するバイオガスへの適用
5 吸着式メタン貯蔵装置
5.1 吸着式メタン貯蔵装置
5.2 吸着式ガス車両
6 総括
o) 石油備蓄
1 はじめに
2 石油精製廃水処理
2.1 活性炭のCOD低減機能
3 特殊活性炭による原油中の微量水銀吸着
3.1 特開平9−40971号特許
3.2 特開平9−221684号特許
3.3 特開平10−72588号特許
p) 同位体分離
1 同位体の用途とその製造法
2 気相吸着における同位体効果
2.1 水素同位体の分離
2.2 水素同位体よりも質量が大きい同位体分子の分離
q) 化学交換法によるリチウム、ホウ素同位体の分離
1 はじめに
2 化学交換法の原理と適用
2.1ホウ素同位体の場合
2.2 リチウム同位体の場合
3 ホウ素同位体の配位子交換による分離
3.1 ホウ素同位体分離用のリガンド
3.2 ホウ素同位体分離のpH依存性
3.3 ホウ素同位体のカラム分離
4 リチウム同位体の分離
4.1 リチウム同位体の分離剤
4.2 リチウム同位体のカラム分離
5 今後の解決すべき課題
r) 光触媒
1 光触媒と光触媒反応
2 光触媒と吸着
3 吸着材と複合化された光触媒
4 吸着材と複合化された光触媒に関する研究事例
5 光触媒と吸着材との複合化
5.1 光触媒とシリカゲルとの複合化
5.2 光触媒とアパタイトとの複合化
5.3 光触媒と活性炭との複合化
6 まとめ
S) 電気二重層キャパシタ
1 はじめに
2 電気二重層キャパシタ(EDLC)と他の蓄電デバイスとの比較
2.1 充放電寿命
2.2 エネルギー密度
2.3 充電時間
2.4 使用温度範囲
3 EDLCに使用される活性炭の製法
3.1 ガス賦活
3.2 薬品(アルカリ)賦活
3.3 第1反応領域、反応温度100~350℃
3.4 第2反応領域、反応温度350~700℃
4 EDLCに適した活性炭性能
5 EDLC用活性炭の最近の動向
6 EDLCの実用例
t) 薬品
1 はじめに
2 特許事例紹介
2.1 特開平10−70993号特許
2.2 特開2002−233398号特許
2.3 特開2006−63004号特許
2.4 特開2006−238773号特許
2.5 特開2006−316025号特許
2.6 その他の事例
u) クリーニング排水処理装置
1 はじめに
2 ドライクリーニング排水
3 処理方法
3.1 曝気法
3.2 気相での活性炭吸着法
3.3 液相での活性炭吸着法
4 装置の仕様
5 装置の構成
5.1 水分離槽
5.2 高分子吸着槽
5.3 調整槽
5.4 曝気槽
5.5 気相吸着槽
5.6 液相吸着槽
6 実証実験結果
6.1 原水及び調整槽、曝気槽の水質
6.2 液相吸着槽の水質
6.3 気相吸着槽
7 おわりに
第2章 吸着現象の基盤技術
1 応用事例における基盤技術
a) ロータ型空調技術
1 吸着材ローター
2 ローター回転式除湿機
3 吸着式デシカント空調プロセス
3.1 装置構成と空調原理
3.2 低温度再生
4 水蒸気吸着材
4.1 汎用吸着材
4.2 除湿用吸着材の開発動向
5 吸着材ローターの数学モデルと数値解析例
5.1 記号および略号
5.2 数学モデル
5.3 数値解析例:吸着等温線形状の影響
b) VOC回収技術
1 はじめに
2 吸着法によるVOC回収技術の現況
2.1 加熱スイングPSA方式
2.2 圧力スイングPSA方式
2.3 繊維状活性炭方式
2.4 ハニカム方式
2.5 流動床方式
3 吸着法によるVOC回収技術の今後の課題
c) 濃縮・精製技術
1 はじめに
2 吸着装置の分類
3 吸着装置の選定と設計
3.1 プロセスガス技術
3.2 水素の精製
3.3 天然ガスの脱湿と脱酸
4 脱水技術
4.1 はじめに
4.2 吸着剤の種類とその特性
4.3 除湿・脱湿操作
d) 天然ガスの精製
1 天然ガスについて
2 天然ガスの精製工程
3 脱炭酸・脱硫・脱水
4 脱水銀
5 都市ガス中の付臭剤
6 合成天然ガスの精製
7 GTL(Gas to Liquid)
e) アフィニティクロマトグラフィー用充填材
1 アフィニティクロマトグラフィーとバイオ生産物分離
2 アフィニティリガンドの選択
3 アフィニティクロマトグラフィー操作
4 アフィニティクロマトグラフィー担体
5 目的物質吸着時の拡散抵抗の小さい担体
f) バイオセンサー
1 バイオセンサーとは?
2 バイオセンサーの作製・利用と吸脱着現象
3 バイオセンサー作製とタンパク質吸着
4 免疫測定における非特異吸着の抑制
5 吸着現象を利用したバイオセンサーの高感度化
6 まとめ
g) 吸着プラントの設計
1 吸着プラント設計のための基本事項
1.1 活性炭吸着除去に関与する因子
1.2 吸着平衡と吸着速度
1.3 プラント設計のためのモデル式
1.4 相似律を利用した固定層吸着過程の迅速評価
1.5 代替指標による計測困難な諸成分の破過予測
1.6 吸着プロセスと他プロセスとの連携
1.7 吸着プラントの一般的諸元
2 産業における応用事例
a) ダイオキシン
1 ダイオキシン類
2 ダイオキシン類除去用活性炭
3 粉末活性炭吹き込み法
4 活性炭吸着塔
5 おわりに
b) 環境ホルモンの概要
1 環境ホルモンの概要
1.1 内分泌撹乱作用のある物質の例
1.2 環境ホルモンの検出方法
1.3 環境ホルモンの除去方法
c) 極微量の健康リスク要因物質の選択的除去技術
1 はじめに
2 主な健康リスク要因とそのリスク削減
3 有害な多原子イオンあるいは分子の選択的認識・捕捉
3.1 多原子陰イオンの選択的認識・捕捉
3.2 有害多原子陽イオンの選択的認識・捕捉
3.3 有害有機分子の選択的認識・捕捉
4 実用化の技術課題
5 おわりに
d) 浄水器
1 概要
2 おいしい水の要件
3 浄水器の種類
3.1 蛇口直結型
3.2 据置型
3.3 ビルトイン型
3.4 ポット・ピッチャー型
4 浄水器の浄水機構
5 浄水器に使用される活性炭
5.1 粒状活性炭
5.2 繊維状活性炭
6 活性炭処理
6.1 残留塩素除去
6.2 トリハロメタン除去
6.3 異臭味除去
【柳澤裕次郎】
第3章 基礎理論
1 吸着現象の基礎
1 気相吸着
1.1 蒸気と超臨界気体
1.2 物理吸着と化学吸着
1.3 物理吸着
1.4 ミクロ細孔への蒸気吸着
1.5 メソ細孔への蒸気吸着
1.6 マクロ細孔あるいは平坦表面への蒸気吸着
1.7 化学吸着
1.8 高圧吸着
2 液相吸着
2 空気分離
1 空気分離のための吸着剤
1.1 ゼオライトモレキュラシーブ(ZMS)
1.2 分子ふるい炭素(CMS)
2 PSAの概要と短サイクル時間近似の考え方
2.1 PSAの概要
2.2 PSAの各種型式
2.3 短サイクル時間近似の概念
2.4 吸着速度式
3 空気分離PSAの設計
3.1 基礎方程式
3.2 物質収支式の解法
3.3 速度式の解法
3.4 計算例
4 合成ゼオライト(ZMS)を用いた空気分離
4.1 ZMSによる酸素濃縮
4.2 ZMSによる窒素濃縮
4.3 ZMS吸着塔の所要高さ
5 分子ふるい炭素(CMS)を用いた空気分離
5.1 CMSによる窒素濃縮
5.2 CMSによる酸素濃縮
5.3 CMS吸着塔の所要高さ
6 CMS塔とZMS塔の組み合わせによる改善
7 あとがき
3 電気化学吸着
1 はじめに
2 電気化学吸着の基礎
2.1 ファラデー過程と非ファラデー過程
2.2 非ファラデー過程における吸着
2.3 ファラデー過程における吸着
3 電気二重層キャパシタ
3.1 電気二重層キャパシタの原理と特徴
3.2 電気二重層キャパシタの種類
3.3 電気二重層キャパシタ用炭素材料
第4章 吸着操作における異常現象と対策
1 液相吸着におけるクレーム事例対策
1 総論
2 クレーム事例と対策
2.1 活性炭処理水pHの異常上昇
2.2 炭層の微生物障害(その1)
2.3 炭層の微生物障害(その2)
2.4 金属腐食
2.5 その他の障害事例
2 気相吸着における異常現象と対策
a) 活性炭の災害とその対策
1 はじめに
2 活性炭に関する災害事例
3 活性炭の危険物性
3.1 発火の危険性
3.2 爆発の危険性
3.3 中毒の危険性
3.4 酸欠の危険性
3.5 かび、菌の危険性
3.6 装置腐蝕の危険性
4 気相用途での事故例
4.1 溶剤回収塔の発火事故 原因と対策
4.2 輸送中の発火事故 原因と対策
4.3 ハロゲン化合物添着炭のダンパー腐蝕 原因と対策
5 おわりに
b) 防毒マスク
1 防毒マスクの用途と機能
1.1 防毒マスクの主な用途
1.2 防毒マスクが対象とする有毒ガスの種類と吸収缶の種類
1.3 化学物質の空気中濃度による有害性の指標
2 呼吸用保護具としての防毒マスクの特性
2.1 ろ過式呼吸用保護具としての特性
2.2 防毒マスクの構造と機能
2.3 吸収缶の構造と性能
2.4 吸収缶の規格と試験条件
3 特殊用途の防毒マスク
第5章 特許情報から見た用途の拡大
1 吸着 and 半導体
2 吸着 and ウェハ
3 吸着 and 基板 and 洗浄
4 吸着 and エレクトロニクス
5 吸着 and 電池
6 吸着 and キャパシタ
7 吸着 and 食品
8 吸着 and 貴金属
9 吸着 and 薬剤
10 吸着 and 医療
11 吸着 and 車








