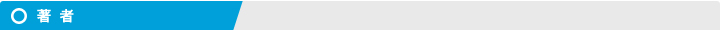
宮岡 徹 静岡理工科大学
熊本 賢三 明治国際医療大学
榎原 智美 明治国際医療大学
北田 亮 自然科学研究機構
黒木 忍 日本電信電話(株)
渡邊 淳司 日本電信電話(株)
白土 寛和 慶應義塾大学
前野 隆司 慶應義塾大学
何 昕霓 日本電信電話(株)
佐藤 克成 奈良女子大学
野々村 美宗 山形大学
永野 光 名古屋大学
岡本 正吾 名古屋大学
坂本 真樹 電気通信大学
望山 洋 筑波大学
佐野 明人 名古屋工業大学
下条 誠 電気通信大学
篠田 裕之 東京大学
大村 吉幸 東京大学
武縄 悟 神戸市立工業高等専門学校
多田 泰徳 名古屋工業大学
大岡 昌博 名古屋大学
神山 和人 電気通信大学
金子 真 大阪大学
日高 佑輔 慶應義塾大学
嵯峨 智 筑波大学
田中 由浩 名古屋工業大学
東 輝明 ニッタ(株)
坂本 富士見 (有)シスコム
河原 宏太郎 イナバゴム(株)
河邊 憲次 シーエムシー技術開発(株)
野村 俊夫 (株)トリニティーラボ
Jeremy A. Fishel SynTouch LLC
Chia-Hsien Lin SynTouch LLC
Raymond Peck SynTouch LLC
Gerald E. Loeb SynTouch LLC
山本 晃生 東京大学
昆陽 雅司 東北大学
塩川 雄太 慶應義塾大学
梶本 裕之 電気通信大学
澤田 秀之 香川大学
韓 星民 福岡教育大学
竹内 伸 富士ゼロックス(株)
坂井 忠裕 NHK放送技術研究所
半田 拓也 NHK放送技術研究所
稲見 昌彦 慶應義塾大学
野嶋 琢也 電気通信大学
井野 秀一 (独)産業技術総合研究所
牧野 泰才 慶應義塾大学
筧 康明 慶應義塾大学
南澤 孝太 慶應義塾大学
仲谷 正史 日本学術振興会 慶應義塾大学
三原 聡一郎 (元)山口情報芸術センター インターラボ
鈴木 理絵子 (株)ファセテラピー 慶應義塾大学
鈴木 泰博 名古屋大学 慶應義塾大学
※初版と内容変更のない項目の著者は初版発刊時(2010年9月)の所属を記載しています。

「触覚」技術が脚光を浴び始めて久しい。近年は学会会場が満杯になるほどの活況を呈している。また、携帯端末、パソコン、家電、自動車、コスメティック、日用品、文房具、飲料、医療・福祉用品など、人が触る様々な製品に携わる産業界の方々からの「触覚」技術への引き合いが近年急増している。
学会での活況の理由としては以下のようなものが考えられる。ロボット分野においては、高度な歩行ロボット、マニピュレータ、視聴覚情報処理、知的情報処理が実現されつつある。一方、「痛み」「心地よさ」「接触状態」「固着・滑り状態」など、身体にとって基本的な情報を検出するためにロボットの全身に高度な触覚センサを配置する必要があるにもかかわらず、触覚センシング技術は発展途上にあった。その原因の一つとして、人間の触覚メカニズムの解明が、視聴覚メカニズムの解明に比べて萌芽的な段階にあったことがあげられる。また、作成が困難であったこともあげられる。バーチャルリアリティー分野においても、同様な構造が見られる。安全性、快適性、エンターテイメント性のために触覚技術が視聴覚と同様に重要と考えられるにもかかわらず、である。このため、未踏の触覚技術の「面白さ」が研究者・技術者を引き付けて止まないのである。
産業界からの引き合いの急増も、同様な理由が考えられる。上述の携帯端末・・・の直接の目的は、いずれも触覚ではなかった。携帯端末は視聴覚情報の伝達、自動車は移動、化粧品は見た目、飲料は味が重要であった。これら、製品のプライマリーな用途に関する研究開発が進展し、技術が飽和しつつある現在、新たな付加価値のチャンネルとして触覚技術が見直されているという側面がある。また、他の技術は飽和しつつあるのに対し、触覚技術は未開のフロンティアであるため、大きな可能性を秘めていると直感されるという側面もある。
以上のような触覚技術への期待の高まりに伴い、計測自動制御学会システムインテグレーション部門に触覚部会(本書の編者は触覚部会の元主査である)が設立されるなど、学術界では触覚関連技術は近年大きく進展した。しかし、触覚技術を学問として体系化するための試みはこれまで十分に行われてきたとはいえなかった。このため、初学者や実践技術者は、学会に参加したり専門的な論文を調査するなどの高いハードルをクリアしなければ触覚技術の全貌を理解できないのが現状であった。
このような状況に初めて応えたのが本書である。すなわち、本書は、世界で初めて、ヒトの触覚認識メカニズム、触の錯覚の基本から、触覚センサ、触覚ディスプレイへの応用、そして触覚技術の応用展望まで、学術界から企業まで、技術のSEEDS(種)からNEEDS(必要性)まで、生理学、心理学、脳神経科学、計算科学から工学まで、様々な分野の内容を体系的・網羅的に述べたものである。しかも、入門書としての基礎的事項から研究開発の最先端まで、それぞれの分野の第一人者が執筆している。このため、本書は、工学、心理学、脳神経科学、医学・生理学から製品開発、生産技術、マーケティング、デザイン、アートにわたる初学者から実践技術者、専門家まで、触覚技術に興味を持たれた様々な分野の技術者・研究者の方々にとって有益な内容に満ちていると信ずる。また、視聴覚や味覚・嗅覚などの他の感覚の研究者・技術者の方、感覚ではなく運動・行動・認知等の研究者・技術者の方にとっても、アイデアとヒントに満ちた本になったと信ずる。
2010年9月の発刊後、触覚技術を調査・情報収集する中で、最終的に本書に辿りついたという声をよく耳にする。また、本書を教材とした触覚講習会は、執筆者でもある第一線の研究者が講師として登壇し、年々活況を増している。合わせて、体験デモで実際に触ってみることで、その真の価値をご理解頂けている。一方で、未掲載の内容も散見され始め、今回、『増補版』として内容の充実を図ることとなった。まず、第1章は、機械受容器の構造、時空間知覚における情報統合、温冷覚、材質感次元、触覚のオノマトペなどが加わり、さらに基礎的内容が充実した。第3~4章は、製品化されたものを含め最新の触覚センサと触覚ディスプレイの情報が盛り込まれた。第5章では、触覚と記号といった新たな考え方が示された。また、第6章として、触覚教育と普及が新たに章立てされ、よりオープンな活動が紹介された。
本書が触覚認識メカニズムと触覚センサ・触覚ディスプレイ技術発展のための礎となり、本分野のさらなる発展に寄与することを切に祈る。
(「はじめに」より抜粋)








