
日本語版発刊のことば
ナノテクノロジーというのは,ナノメートル領域(1~1100nm,10-9~10-7m)の微細なスケールの物質を対象とし,この微細な物質(ナノ材料)の構造を積極的に操って,新たな機能や性質を生み出し,利用する技術である。
ナノテクノロジーの概念は,1959 年に米国の物理学者のリチャード・ファインマン博士によりはじめて提唱された。彼は,当時24 巻のブリタニカ大百科事典の情報を針の先ほどの微小空間に蓄えることができる技術を講演で予言した。
21 世紀の始まりとともに,ナノテクノロジーは社会に多大な恩恵をもたらす革新的先端技術として期待され,日米欧をはじめ,世界各国において科学技術の重要分野として位置づけられている。
ナノテクノロジーの進歩により,ナノレベルでのいろいろな現象がわかるようになり,さらには分子や原子を見るだけでなく,それを操作する技術も発展してきた。その応用分野はIT だけでなく,医療・バイオ,環境・エネルギー,新材料・素材と幅広い分野に広がっている。
ナノテクノロジーの進展に伴い,環境ナノテクノロジー分野への活用も注目されるようになった。環境ナノテクノロジーにとって最優先のテーマは,ナノ材料を活用した,汚染物質の排出抑制や汚染物質の分解・除去・無害化技術の確立である。
わが国では2000 年代から環境ナノテクノロジーに関し,環境汚染状況のモニタリング,環境汚染物質の有害性の把握・評価,環境汚染物質の分解,除去,および再生可能エネルギー利用という4 つの技術課題を取り上げ研究が進められている。
このような状況の中で,マハトマガンジー大学副学長であるサブ・トーマス博士が編集した“Nanotechnology for Environmental Remediation”は,ナノ材料を活用して環境を修復する“ナノレメディエーション”という新たな分野における現状と今後の有望な大きな展開を22 の寄稿論文を通して読者に紹介している。
具体的には,さまざまな汚染物質の環境修復に用いられる金属ナノ粒子,ポリマーナノ粒子,カーボンナノチューブ,デンドリマー,植物・微生物・酵素機能を組み込んだナノバイオ粒子等さまざまな機能性ナノ材料やナノ複合体の開発の現状,ならびに水,大気,土壌汚染で問題となっている,温室効果ガス,有機塩素化合物,油・染料等の有機汚染物質,鉛・ヒ素等の重金属,医薬品,病原微生物および農業利用等へのナノレメディエーションの活用に焦点を当てている。さらにナノテクノロジーのリスクアセスメントやナノバイオレメディエーションのLCA についても記載されている。
執筆者らは,土壌浄化,水処理,大気処理などの分野で,ナノテクノロジー,ナノ吸着剤,ファイトナノテクノロジーなどの先進的なツールを用いて研究を行っている第一人者たちであり,彼らの研究に裏打ちされた斬新なアイデアと多くの情報が紹介されている。多くの技術は,基礎から実用化を目指した段階のものが多いが,ナノレメディエーションが従来の方法に代わる効果的な環境修復技術として大変魅力的で有望であることを示している。
本書は,環境浄化に携わる技術者,施工者,規制担当者,研究者および学生にナノレメディエーションの面白さならびに大きな発展の可能性を秘めていることを気づかせる書である。
2024年10月
監訳 矢木 修身
翻訳 大前 奈月
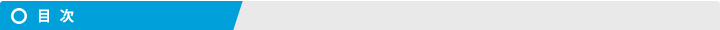
序 文
まえがき
日本語版発刊のことば
第1章
ナノ材料の科学と技術:はじめに
Merin Sara Thomas, Sabu Thomas and Laly A. Pothen
1.1 はじめに
1.2 ナノ材料の分類
1.3 ナノ材料の種類
1.3.1 有機ナノ粒子
1.3.2 無機ナノ粒子
1.3.3 炭素系ナノ粒子
1.4 ナノ材料の特性
1.4.1 サイズと表面積
1.4.2 機械的特性
1.4.3 光学的および電気的特性
1.4.4 磁気特性
1.5 ナノ材料の特性評価
1.5.1 ナノ粒子の表面形状,表面積,サイズ,形状
1.5.2 元素と鉱物の組成
1.5.3 ナノ粒子内の構造と結合
1.6 ナノテクノロジーの現状
1.7 ナノテクノロジーの安全性問題
1.8 結 論
第2章
ナノレメディエーション:簡単な紹介
Renjitha P. Rajan, Merin Sara Thomas, Sabu Thomas and Laly A. Pothen
2.1 はじめに
2.2 ナノレメディエーションの機構
2.3 消毒のためのナノテクノロジー
2.4 重金属とイオンの除去のためのナノテクノロジー
2.5 有機汚染物質除去のためのナノテクノロジー
2.6 油・水分離のためのナノテクノロジー
2.7 ナノレメディエーションの課題
2.8 結 論
第3章
土壌浄化におけるナノテクノロジー
Alice Alex, Sithara Raj, Sunish K. Sugunan and Gigi George
3.1 環境と微生物へのENM の影響
3.2 土壌浄化における人工ナノ材料
3.2.1 鉄系ナノ材料
3.2.2 酸化チタン系ナノ材料
3.2.3 炭素系ナノ材料
3.2.4 シリカ系ナノ材料
3.3 土壌浄化におけるナノテクノロジー
3.3.1 TiO2 ナノ粒子
3.3.2 鉄ナノ粒子
3.3.3 シリカナノ粒子
3.3.4 炭素系ナノ粒子
3.3.5 銀ナノ粒子
3.4 結 論
第4章
水処理のためのナノテクノロジー:
有機・無機化合物の浄化における近年の進捗
Charulata Sivodia and Alok Sinha
4.1 はじめに
4.1.1 ナノ材料の分類と合成ルート
4.2 ナノテクノロジーの応用
4.2.1 重金属除去
4.2.2 染料除去
4.2.3 有機塩素化合物(OCC)の除去
4.2.4 無機陰イオン
4.3 結 論
第5章
大気汚染浄化のためのナノテクノロジー
Haleema Saleem, Syed J. Zaidi, Ahmad F. Ismail and Pei S. Goh
5.1 はじめに
5.2 大気汚染浄化のためのナノテクノロジーの最新動向
5.2.1 ナノ吸着剤
5.2.2 ナノフィルター・ナノ構造膜
5.2.3 ナノ触媒
5.2.4 ナノセンサー
5.2.4.1 NO2 の検出
5.2.4.2 H2S の検出
5.2.4.3 SO2 の検出
5.3 環境へのナノ材料の悪影響
5.4 将来の方向性
第6章
ナノ材料を用いるろ過
Ahmed Ibrahim Abd-Elhamid and AbdElAziz Ahmed Nayl
6.1 はじめに
6.2 空気ろ過におけるナノファイバー
6.2.1 空気ろ過における純粋なナノファイバー
6.2.2 空気ろ過におけるポリマー―ナノファイバー複合体
6.2.3 空気ろ過におけるMOF―ナノファイバー複合体
6.2.4 空気ろ過におけるナノ材料―ナノファイバー複合体
6.2.5 窓用スクリーン
6.3 廃水ろ過におけるナノファイバー
6.3.1 油水分離
6.3.2 目詰まり耐性
6.3.3 有機・無機汚染物質の除去
6.3.4 微生物の除去
6.4 結 論
第7章
ナノ吸着剤による環境修復
Adnan Khan, Sumeet Malik, Sumaira Shah, Nisar Ali, Farman Ali, Suresh Ghotekar,
Harshal Dabhane and Muhammad Bilal
7.1 はじめに
7.2 ナノ材料の特性と合成
7.3 廃水からの汚染物質除去の異なるクラスのナノ吸着剤
7.3.1 炭素系ナノ吸着剤
7.3.2 シリカ系ナノ吸着剤
7.3.3 金属系ナノ吸着剤
7.3.4 ポリマー系ナノ吸着剤
7.4 結 論
第8章
重金属イオン6 価クロムの可視光応答型光触媒分解
Priya Rawat, Harshita Chawla and Seema Garg
8.1 はじめに
8.2 可視光活性のためのTiO2 修飾
8.2.1 遷移金属酸化物のカップリング
8.2.1.1 単純な金属酸化物
8.2.1.2 スピネル型混合金属酸化物
8.2.2 金属硫化物のカップリング
8.2.3 貴金属のカップリング
8.2.4 相乗変換と容量性脱イオン化
8.3 光触媒の安定性
8.4 結 論
8.4.1 現在の状況
8.4.2 課 題
8.4.3 今後の展望
第9章
ファイトナノテクノロジーによる重金属と染料の浄化
Lakhan Kumar, Pragya Kamal, Kaniska Soni and Navneeta Bharadvaja
9.1 はじめに
9.2 環境汚染と健康への影響
9.2.1 重金属とそれに関連する環境・公衆衛生課題
9.2.2 染料と関連する環境・公衆衛生問題
9.3 環境汚染と修復戦略
9.3.1 マイコレメディエーション
9.3.2 ファイトレメディエーション
9.3.3 ファイコレメディエーション
9.3.4 バイオスティミュレーション
9.3.5 ライゾフィルトレーション
9.4 環境汚染物質浄化のためのファイトナノテクノロジーのアプローチ
9.4.1 植物由来ナノ材料の重金属浄化への応用可能性
9.4.2 植物由来ナノ材料の染料浄化への応用可能性
9.5 ファイトナノレメディエーションの展望と課題
9.6 結 論
第10章
表面機能化金ナノ粒子による環境修復
Daniel T. Thangadurai, Nandhakumar Manjubaashini and Devaraj Nataraj
10.1 はじめに
10.2 金ナノ粒子の基礎
10.3 金ナノ粒子の意義
10.4 表面機能化金ナノ粒子の重要性
10.5 金ナノ粒子の応用
10.6 ローダミン6G 機能化金ナノ粒子(Rh6G 金ナノ粒子)の合成と特性評価
10.6.1 還元法によるRh6G 金ナノ粒子の合成
10.6.2 Rh6G 金ナノ粒子の特性評価
10.6.2.1 X 線回折研究
10.6.2.2 形態分析
10.6.2.3 XPS 研究
10.6.2.4 ラマン分光分析
10.6.2.5 熱研究
10.7 ローダミン6G 機能化金ナノ粒子と重金属イオンとの相互作用
10.7.1 選択性と感度の研究
10.7.1.1 時間分解蛍光測定
10.7.1.2 安定性測定
10.8 Rh6G 金ナノ粒子の応用
10.8.1 実水試料分析
10.8.2 細胞毒性試験
10.9 結 論
第11章
金属酸化物ナノ粒子による環境修復
Abhilash Venkateshaiah, Miroslav ?ern?k and Vinod V.T. Padil
11.1 はじめに
11.2 金属酸化物ナノ粒子の合成
11.2.1 物理的方法
11.2.1.1 化学気相合成法
11.2.1.2 レーザーアブレーション法
11.2.1.3 メカニカルミリング技術
11.2.2 化学的方法
11.2.2.1 共沈法
11.2.2.2 ゾル-ゲル法
11.2.2.3 ソルボサーマル法
11.2.3 生物学的方法
11.2.3.1 植物を介した合成
11.2.3.2 微生物による合成
11.3 金属酸化物ナノ粒子を用いた環境修復法
11.3.1 吸 着
11.3.2 触媒作用
11.3.3 抗菌活性
11.4 さまざまな金属酸化物ナノ粒子による修復
11.4.1 酸化チタンナノ粒子
11.4.2 酸化亜鉛ナノ粒子
11.4.3 鉄系酸化物
11.4.4 酸化銅
11.4.5 酸化スズナノ粒子
11.4.6 酸化タングステンナノ粒子
11.4.7 その他の金属酸化物ナノ粒子
11.5 結論と展望
第12章
機能化ナノ粒子による環境修復
Beatriz Jurado-S?nchez
12.1 はじめに
12.2 環境修復のためのナノ粒子と機能化
12.2.1 金属および金属酸化物ナノ粒子
12.2.1.1 銀と金のナノ粒子
12.2.1.2 酸化チタンナノ粒子
12.2.1.3 酸化鉄磁性粒子
12.2.2 シリカと高分子ナノ粒子
12.2.3 炭素ナノ材料
12.2.4 2 次元ナノ材料
12.2.5 マイクロモーター
12.3 機能化ナノ粒子によるナノろ過
12.4 機能化ナノ粒子によるナノ光触媒分解
12.5 機能化ナノ粒子による汚染物質の化学分解
第13章
デンドリマーによる環境修復
Uyiosa O. Aigbe, Kingsley E. Ukhurebor, Robert B. Onyancha, Onoyivwe M. Ama,
Otolorin A. Osibote, Heri S. Kusuma, Philomina N. Okanigbuan,
Samuel O. Azi and Peter O. Osifo
13.1 はじめに
13.2 合成方法
13.2.1 発散アプローチ
13.2.2 収束法
13.3 デンドリマーの物理化学的性質
13.4 デンドリマーの環境応用
13.4.1 機能化デンドリマーを用いた水浄化プロセス
13.4.2 光触媒におけるデンドリマーの応用
13.4.3 土壌浄化におけるデンドリマーの応用
13.4.4 大気浄化におけるデンドリマーの応用
13.5 結 論
第14章
ナノ結晶による環境修復
Muhammad N. Ashiq, Sumaira Manzoor, Abdul G. Abid and Muhammad Najam-Ul-Haq
14.1 はじめに
14.1.1 環境修復技術
14.1.1.1 光触媒作用
14.1.2 環境修復に用いられるさまざまな種類のナノ材料
14.1.2.1 金属酸化物系ナノ構造
14.1.2.2 ナノ複合体系光触媒
14.1.2.3 磁性ナノ材料
14.1.3 効率的な抗菌剤としてのナノ構造材料
第15章
酵素ナノ粒子による環境修復
Neha Tiwari and Deenan Santhiya
15.1 はじめに
15.2 環境修復に用いられる各種酵素の供給源
15.3 環境修復のためのさまざまな酵素固定化ナノ粒子
15.3.1 磁性ナノ粒子
15.3.2 メソポーラスナノ粒子
15.3.3 炭素系ナノ粒子
15.3.4 カーボンナノチューブ
15.3.5 環境修復におけるナノ粒子の役割
15.4 修復における酵素ナノ粒子の重要性
15.4.1 酵素ナノ粒子の利点
15.5 酵素ナノ粒子によるバイオレメディエーションの課題
15.6 結 論
第16章
ナノファイバーによる環境修復
Daniel Pasquini, Lu?s C. de Morais and Pedro E. Costa
16.1 はじめに
16.2 セルロース
16.2.1 化学構造と反応性
16.2.2 セルロースナノファイバーの起源
16.2.3 セルロースナノファイバーの表面修飾
16.2.4 セルロースナノファイバー表面の改質処理
16.3 汚染物質除去プロセスにおけるナノファイバーの利用
16.3.1 染料へのナノレメディエーション
16.3.2 Pb(II) へのナノレメディエーション
16.4 結 論
第17章
バイオインスパイアードナノ複合体による医薬品汚染物質の浄化
Pavan K. Gautam, Saurabh Shivalkar, Anirudh Singh, M. Shivapriya Pingali,
Shrutika Chaudhary, Sushmita Banerjee, Pritish K. Varadwaj and Sintu K. Samanta
17.1 はじめに
17.2 医薬品による環境有害性
17.3 ナノ材料合成のメカニズム
17.3.1 金属塩の生物還元と合成したナノ材料のキャッピング
17.3.1.1 タンパク質による金属塩の還元
17.3.1.2 多糖類による金属塩の還元
17.3.2 ナノ粒子の合成に影響するさまざまなパラメーター
17.3.3 ナノ粒子の製造に応用される生物
17.3.3.1 細菌を用いた合成
17.3.3.2 真菌を用いた合成
17.3.3.3 藻類を用いた合成
17.3.3.4 植物を用いた合成
17.4 医薬品汚染物質の除去に用いられるさまざまなバイオ加工ナノ材料
17.4.1 生物起源パラジウムナノ粒子
17.4.2 生物由来マンガンナノ粒子
17.4.3 単一金属/バイメタルナノ複合体
17.5 医薬品の基本的な分解機構
17.6 まとめ
第18章
ナノ材料とその薄膜による光触媒空気浄化
Juliane Z. Marinho and Antonio Otavio T. Patrocinio
18.1 屋内外の空気浄化技術
18.2 空気浄化のための光触媒分解機構
18.3 空気浄化に用いられる光触媒
18.3.1 金属酸化物
18.3.2 三元酸化物
18.3.3 金属硫化物
18.3.4 金属を使わない材料
18.4 空気浄化用光触媒の高効率化戦略の構築
18.4.1 ドーピングによる光触媒の化学修飾
18.4.2 表面ヘテロ構造による修飾
18.4.3 大気汚染に対する光触媒材料の大規模応用
18.5 結論と展望
第19章
エアロゲルによる環境修復
Abdul S. Jatoi, Zubair Hashmi, Nabisab Mujawar Mubarak, Faisal A. Tanjung,
Muhammad Ahmed, Shaukat A. Mazari, Faheem Akhter and Shoaib Ahmed
19.1 はじめに
19.2 空気清浄におけるエアロゲルの応用
19.2.1 CO2 回収におけるエアロゲル
19.2.2 揮発性有機化合物(VOC)除去におけるエアロゲル
19.3 水処理へのエアロゲルの応用
19.3.1 石油と有毒有機化合物の浄化におけるエアロゲル
19.3.2 重金属イオン除去におけるエアロゲル
19.4 結論と展望
第20章
ナノ材料の環境毒性学:進歩と課題
Wells Utembe
20.1 環境毒性学とナノテクノロジー
20.2 ナノ材料の環境毒性-概要
20.3 ナノ毒性学:現在のアプローチ,問題,および課題
20.3.1 環境毒性学におけるナノ材料の特性評価
20.3.2 ナノ材料のin vivo 毒性学的評価におけるアプローチと技術
20.3.2.1 ナノ材料のin vitro 毒性試験における線量測定
20.3.3 ナノ材料のin vitro 毒性学的評価における方法と技術
20.3.3.1 ナノ材料のin vitro 毒性試験における作業量測定:進歩と課題
20.3.4 ナノ材料のin silico 毒性:定量的構造活性相関(QSAR)
20.3.5 ナノ毒性学における用量反応
20.3.5.1 生理学的薬物動態(PBPK)モデルの役割と応用
20.4 結 論
第21章
ナノ材料の社会的影響
Paolo Di Sia
21.1 はじめに
21.2 ナノ材料の社会的・環境的影響
21.3 ナノ材料に関連する健康と安全性
21.4 食品分野
21.5 知的財産について
21.6 ナノテクノロジーと発展途上国
21.7 社会正義と市民の自由について
21.8 結 論
第22章
バイオレメディエーションのためのナノ材料のLCA
Garima Pandey, Reeta Chauhan, Ajay S. Yadav and Sangeeta Bajpai
22.1 はじめに
22.2 ナノバイオレメディエーション
22.3 ナノバイオレメディエーションの効果
22.4 ナノ粒子の生合成
22.5 LCA とは
22.5.1 ナノバイオレメディエーションに適用されるLCA
22.5.2 ナノバイオレメディエーションのLCA 研究の段階
22.5.2.1 インベントリー
22.5.2.2 影響評価
22.5.2.3 正規化と解釈
22.5.3 課題と将来展望
22.6 結 論
索 引








