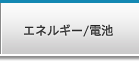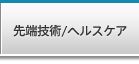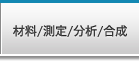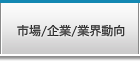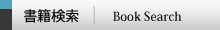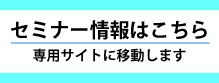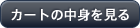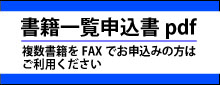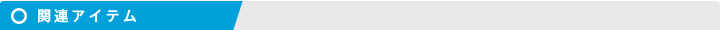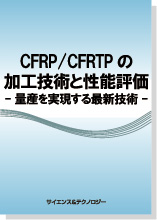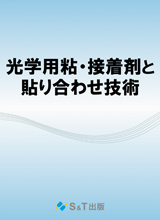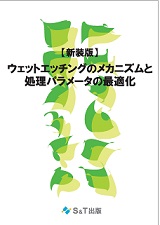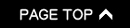セミナー12/17 異種材料接着・接合の基礎と強度・信頼性・耐久性評価法およびトラブル対策
異種材料接着・接合の基礎と強度・信頼性・
耐久性評価法およびトラブル対策
![]() PDFパンフレット(セミナー「異種材料接着・接合の基礎と強度・信頼性・耐久性評価法およびトラブル対策」)
PDFパンフレット(セミナー「異種材料接着・接合の基礎と強度・信頼性・耐久性評価法およびトラブル対策」)
主 催
S&T出版株式会社
日 時 ・ 場 所
日時:2015年12月17日(木) 10:30~16:30
会場:高橋ビルヂング(東宝土地(株)) 3F 会議室 (東京都千代田区神田神保町3-2)
→会場へのアクセス
受 講 料 (税込)
49,800円 Eメール案内会員価格 47,300円 ※昼食・資料代を含む
<1名様分の受講料で2名様まで受講できます。>
※2名様ご参加は同一会社・法人からの同時申込に限ります。
※2名様ご参加は2名様分の参加申込が必要です。ご連絡なく2名様のご参加はできません。
※3名様以上のご参加は、追加1名様あたり10,800円OFFになります。
Eメール案内登録をしていただいた方には、Eメール案内会員価格を適用いたします。
→複数名同時申込はこちらの用紙(PDF)をご利用ください。
講 師
鈴木 靖昭 氏 / 鈴木接着技術研究所 所長 工学博士 技術士(機械部門 構造接着)
【略歴】
昭和40年3月 名古屋工業大学 工業化学科卒業
昭和40年4月 日本車輌製造(株)入社 技術研究所~開発本部に38年間在職中、主として、高圧発電機絶縁用エポキシ樹脂の研究開発、新幹線などの鉄道車両に関する有機材料、接着接合部のFEM応力解析、破壊条件、強度、信頼性および耐久性に関する研究・評価、有機材料等の評価、故障原因究明等に従事
平成15年3月 日本車輌製造(株)定年退職(最終役職:開発本部部長)
平成15年4月~平成20年12月 日本車輌製造(株)開発本部勤務(非常勤)
平成21年1月~平成22年7月 日本車輌製造(株)鉄道車両本部 技術部勤務(非常勤)
平成15年4月~平成23年3月 名城大学非常勤講師
平成15年4月~平成25年3月 中部大学非常勤講師
平成26年4月 公益財団法人 名古屋産業振興公社 テクノアドバイザー
平成26年7月 公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター アドバイザー
平成26年11月 とよたイノベーションセンター アドバイザー
【学会活動】
日本接着学会:構造接着研究委員会 応力解析分科会幹事、接着設計研究委員会委員、アメリカ接着視察団幹事など合せて30年以上活動
日本機械学会:接着接合技術応用研究分科会委員として5年間活動、機械材料・材料加工部門 運営委員会委員
色材協会:現在まで30年以上にわたり、理事、評議員、審議委員、運営委員として活動
日本材料学会:高分子材料部門委員会委員
【著書等】
著書(共著):26冊、学術論文(共同研究を含む):22報、セミナー・受託講演:56件、学会発表(共同研究を含む):51件(詳細内容は鈴木接着技術研究所HP:http://www.s-adhesion-tech.com/をご参照ください)
趣 旨
信頼性が高く耐久性が大きく強い異種材料接着・接合継手を設計することを目的とする人に対し、接着力発現の原理、接着剤および表面処理法の理論的選定法、異種材料の接着、樹脂射出一体成型法、レーザ溶接法など最新の接合法について解説します。また、各種継手に発生する応力分布、変形、および破壊条件の解析法、それに基づく強い接着構造の設計法、負荷応力の時間的分布と接着強度のばらつきに基づいた(ストレス-強度モデルによる)継手の希望破壊確率を与える安全率の計算法、接着継手の劣化の主要原因である温度、湿度、機械的応力などのストレスと劣化速度との理論的関係およびそれに基づいた加速試験による寿命予測法について詳しく解説します。さらに、各種接着強度評価法、接着トラブル事例、その原因別分類と対策についても解説し、最後にご質問に対し講師の45年間にわたる接着についての実務経験に基づき、ご回答いたします。
プログラム詳細
1. 接着力発現の原理
1.1 化学的接着説
①原子・分子間引力発生のメカニズム
②接着剤の役割
1.2 機械的接合説(アンカー効果)
1.3 からみ合いおよび分子拡散説
1.4 接着仕事
1.5 シーリング材の接着力発現の原理と役割
1.6 粘着剤の接着力発現の原理と役割
2. 各被着材に適した接着剤の選定法
2.1 Zismanの臨界表面張力
2.2 溶解度パラメーターによる接着剤の選定
①物質の溶解度パラメーター
②2種類の液体が混合する条件(非結晶材料に適用)
③結晶性高分子が難接着性である理由とそれを解決するための表面処理法
3. 接着剤の種類、特徴、および最適接着剤の選定法
3.1 各接着剤の種類と特徴
①耐熱航空機構造用接着剤
②エポキシ系接着剤(液状)
③ポリウレタン系接着剤(室温硬化型)
④アクリル系接着剤(SGA)
⑤耐熱性接着剤
⑥吸油性接着剤
⑦紫外線硬化型接着剤
⑧弾性接着剤
⑨短時間接着剤
3.2 接着剤の耐薬品性および耐候性について
3.3 各種接着剤のせん断およびはく離接着強度特性
3.4 選定のための接着剤性能表
3.5 各種被着材に適した接着剤の選び方
3.6 各種シーリング材の性能および用途
4. 被着材に対する表面処理法の選定法
4.1 各種表面処理法およびその特徴
4.2 金属の表面処理法
①炭素鋼
②ステンレス鋼
③アルミニウム
④銅およびニッケル箔の表面処理状態とはく離エネルギーとの関係
⑤化学的粗面化(ケミブラスト)
4.3 プラスチックの表面処理
①洗浄および粗面化
②プラズマ処理
③コロナ放電処理
④UV/オゾン処理
⑤火炎処理
⑥各種表面処理方法
⑦プライマー処理
⑧難接着性結晶性エンジニアリングプラスチックの表面処理法
5. 最新の異種材料接合法
5.1 金属の湿式表面処理-接着・加硫法
:ケミブラスト®〔日本パーカライジング(株)〕
5.2 金属の湿式表面処理-接着法
:NAT〔大成プラス(株)〕
5.3 金属の湿式表面処理-樹脂射出一体成形法
:NMT〔大成プラス(株)〕
:新NMT〔大成プラス(株)〕
:PAL-fit〔日本軽金属(株)―ポリプラスチック(株)〕
:アルプラス〔コロナ工業(株)〕
:アマルファ〔メック(株)〕
:TRI〔東亜電化(株)〕
:Quick10〔ポリプラスチック(株)〕
5.4 金属のレーザ処理-樹脂射出一体成形法
:レザリッジ®〔ヤマセ電気(株)-ポリプラスチック(株) 〕
:D LAMP®〔(株)ダイセル〕
5.5 フィラー強化樹脂のレーザ処理-異材樹脂射出成形法
:AKI-Lock®〔ポリプラスチック(株)〕
5.6 金属―樹脂レーザ接合法
:LAMP〔大阪大学〕
:金属の陽極酸化処理-樹脂のレーザ接合法〔名古屋工業大学〕
:金属のPMS処理-金属・樹脂の大気圧プラズマ処理-レーザ接合法〔あいち産業科学技術総合センター,名古屋工業大学,輝創(株)〕
5.7 インサート材使用の樹脂-異種材料レーザー接合法 〔岡山県工業技術センター,早川ゴム(株),岡山大学〕
5.8 樹脂同士の加熱溶着
:電気抵抗溶着〔新明和工業〕
:電磁誘導加熱〔ポリプラスチックス(株)〕
5.9 摩擦重ね接合(FLJ)〔大阪大学〕
5.10 超音波接合
5.11 熱板接合
5.12 金属・セラミックス・樹脂の化学接合法(接着剤レス)
:CB処理〔新技術研究所(ATI)〕
5.13 樹脂とゴムの架橋接着
:ラジカロック〔中野製作所,ダイセル・エボニックス(株)〕
5.14 分子接着剤 〔岩手大学工学部,(株)いおう化学研究所〕
6. 射出成形および融着における接着力発現のメカニズム
6.1 エッチングまたはレーザー照射により被着材表面に微細凹凸を形成して接着力を向上させる場合
①マルチスカーフジョイント効果
②マルチラップジョイント効果
③アンカー効果
④被着材のエッチングにより継手の耐久性が向上する理由
6.2 樹脂同士の融着による接合の場合の接着強度発現のメカニズム
①一方の樹脂のみが溶融する場合
②両方の樹脂が溶融する場合
7. 接着継手形式および負荷外力の種類
7.1 接着接合の長所と短所
7.2 各種接着継手形式
7.3 接着部加わる外力の種類
8. 各継手の応力分布および強度評価
8.1 重ね合せ継手
①応力解析結果(解析解およびFEM)
②エネルギーバランス式
③Al被着剤のせん断破壊荷重に関する実験および弾塑性FEM解析による検討
④バルク接着剤の容積と引張強度および接着層厚さと接着強度との関係
8.2 スカーフおよびバット接着継手のFEM応力解析および混合モード条件下の破壊条件
①応力解析法
②スカーフ継手の混合モード条件下の接着強度実験値および破壊条件の検討
③接着強度の変動係数
④破面解析
8.3 はく離応力の解析
①可撓性被着材のはく離による応力分布
②はく離角度による応力分布の変化
③線形弾性エネルギーバランスによるせん断強度とはく離強度の統一的解析
8.4 スポット溶接-接着併用継手のFEM応力解析結果
8.5 FEM構造解析による接着接合部の変形および強度評価方法
①特異応力の強さを用いたバット継手の引張接着強度の評価例
②結合力モデル(CZM)解析法と混合モード破壊クライテリオンを用いた単純重ね合せ継手の解析例
9. 最適接合部の設計
9.1 強い接着接合部を設計するための一般的留意事項
9.2 接着接合部の選択
①板の接合構造
②ハット形補強材の接合構造
③はく離力への対応策
④管および棒の接着接合部の設計例
10. 経年劣化(強度低下およびばらつき増加)による故障率の増加について(ストレス-強度のモデル)
11. 所定年数使用後の接着接合部に要求される故障確率確保に必要な安全率の計算法
11.1 正規分布について
11.2 負荷応力(ストレス)が一定値の場合の安全率の計算法
11.3 負荷応力(ストレス)が分布する場合の安全率の計算法
11.4 航空機において安全率が小さく取られる理由(強度のばらつきと故障率との関係)
11.5 正規確率紙を用いた接着強度の標準偏差および変動係数の求め方
11.6 各種接着継手の静的強度の変動係数実験値
12. 接着接合部劣化の3大要因
12.1 接着界面へ水分が浸入することによる劣化の促進
12.2 温度による物理的および化学的劣化の加速
12.3 応力による物理的および化学的劣化の加速
13. アレニウスモデル(温度条件)による耐久性加速試験および寿命推定法
13.1 化学反応速度式と反応次数
13.2 濃度と反応速度との関係
①0次反応の場合
②1次反応の場合
③2次反応の場合
13.3 材料の寿命の決定法
13.4 反応速度定数と温度との関係
13.5 アレニウス式を用いた寿命推定法
13.6 加速係数
14. アイリングモデルによるストレス、湿度負荷、および水浸漬条件下の耐久性加速試験および寿命推定法
14.1 アイリングの式を用いた寿命推定法
14.2 アイリング式を用いた湿度に対する耐久性評価法
①絶対水蒸気圧モデル
②相対湿度モデル1
③相対湿度モデル2(Lycoudesモデル)(寿命予測の具体例)
14.3 温度・湿度・応力負荷条件下の耐久性評価法(Sustained Load Test)と実験結果
14.4 JIS K 6867接着剤-構造接着接合品の耐久性試験方法-くさび破壊法(ウェッジテスト)による耐湿および耐水性試験方法
14.5 アルミニウム合金のエッチングと耐久性との関係
①アルミニウムのエッチングにより生成した酸化皮膜
②アルミニウムのエッチング法と耐久性との関係
15. 金属/接着界面の耐水安定性についての熱力学的検討
16. 接着接合部の疲労試験方法および疲労試験結果
16.1 アイリング理論から誘導されるS-N曲線
16.2 マイナー則(線形損傷則)
16.3 接着継手、スポット溶接-接着併用継手、リベット-接着併用継手の疲労試験結果
17. 接着接合部のクリープ破壊強度およびクリープ試験方法
17.1 クリープ破壊強度、破壊時間-温度の関係式(ラーソン-ミラー式)
17.2 実験値からラーソン-ミラー式の決定方法
17.3 プラスチックのラーソン-ミラー線図例
17.4 継手のクリープ試験方法
18. 接着トラブルの原因別分類と対策
18.1 原因別分類とその対策(表の解説)
18.2 各種トラブル事例の原因と対策(テキスト内容を概説)
□質疑応答・名刺交換□